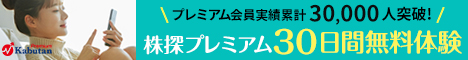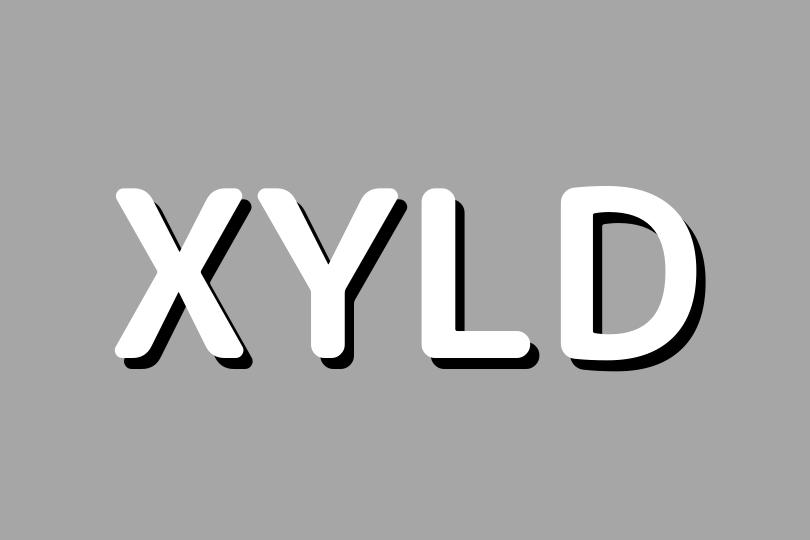病院に行き、ある日突然聞いたことも無い病気を告げられると不安ですよね。
もし難病と診断されたら特定医療費(指定難病)受給者証の手続きをしましょう!
※令和3年9月時点で指定難病の数は333種類あります。
指定難病とは

平成26年5月に「難病患者に対する医療等に関する法律」(難病法)が成立し、平成27年度1月より施行されました。
この法律で、医療費助成の対象とする疾患は指定難病と呼ばれるようになりました。
特定疾患の新規診断は、難病法の規定により難病指定医のみが新規診断を行うことになり、注意が必要です!
難病の申請を最初にする際には、難病指定医に診察を受けに行く必要があります。大学病院などの大きな病院には、必ず難病指定医の先生がいます。
各都道府県の病院はこちら→難病情報センター-難病指定医療機関・難病指定医のご案内
指定難病の一覧
指定難病の一覧→難病情報センター
指定難病のリスト(エクセル)→指定難病リスト.xlsx
※エクセルは難病情報センターにあるデータをダウンロードしたものです。
特定医療費(指定難病)受給者証の新規手続きに必要な書類

申請から特定医療費受給者証交付まで約3ヶ月程度かかりますので、その間に指定医療機関においてかかった医療費は払い戻し請求ができるので、領収書などは保管しておいてください。
特定医療費(指定難病)受給者証に必要な書類は以下の通りです。
診断書(臨床調査個人票)
- 各都道府県の難病指定医が作成した臨床調査個人票が必要となります。
- 住んでいる都道府県以外の難病指定医療機関での臨床個人調査票は作成可能ですが、臨床個人調査票は住んでいる都道府県の用紙を使用します。
申請書(特定医療費支給認定申請書)
- 住民登録している地域の保健所等でもらえます。
- 個人番号(マイナンバー)が必要となります。
住んでいる地域の保健所の検索はこちら→保健所管轄区域案内
住民票
- 発行から3ヶ月以内のもの
- マイナンバー記載のもの
- 申請者と同じ医療保険(国保・社保等)に加入している人が記載されていること
市町村民税(非)課税証明書
- 世帯の課税状況を確認できる書類
保険証の写し
- 被保険者証・被扶養者証・組合員証など、医療保険の加入関係を示すもの
- 申請者と同じ医療保険(国保・社保等)に加入している人の保険証
※各都道府県によってはこの他にも書類が必要な場合がありますので、各都道府県の窓口(福祉課・保健所等)に確認してください。
特定医療費(指定難病)受給者証が届いたら
受給者証が届いたら自己負担上限月額を確認しましょう!
同月内に難病で指定医療機関かかったときの医療費の月額上限が記載されています。

受給者証と一緒に自己負担上限額管理表が送られてくるので、難病で指定医療機関などにかかるときは支払いの時に提出してください。
更新の時に自己負担上限額管理表があるとスムーズに更新ができます。
特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間

原則、申請日から1年以内の期間で、特別な事情がある場合は1年3ヶ月を超えない範囲で定められています。
1年ごとに更新の申請手続きが必要です。
特定医療費(指定難病)受給者証の更新に必要な書類
更新案内が受給者証の期限が切れる前に自宅に届きます。
届いた書類の中身を確認して、必要な書類を集めましょう。
必要なモノ
- 臨床個人調査票☆
- 特定医療費受給者証の写し☆
- 自己負担上限額管理表の写し☆
- 市町村民税が確認できる書類
- 健康保険証の写し
- 指定難病に関する医療費総額を確認できる書類(自己負担上限額管理表)
- 生活保護受給者等の証明書類
- 同一保健世帯内に按分対象者がいることを示す書類
必要な書類は、新規の申請と書類内容はほぼ一緒です。
☆マークの付いている書類は更新者全員必要です。
更新申請と同時にできる変更申請
更新申請と同時に変更申請もできます。
変更できる申請
- 氏名・住所・送付先の変更
- 病院の追加・変更
- 病名の追加・変更
- 加入健康保険の変更(国保⇄社保など)
- 自己負担上限月額の変更
自己負担上限月額については、所得・収入の減少など条件が必要な場合もあります。
特定医療費受給者証の使いた方
病院の受診後に会計時に自己負担上限額管理表と一緒に提出します。
自己負担上限額管理表に月に支払った金額を書いてくれるので、もし月の上限を超えたら同月内は同じ病気の受診料が無料になります。
院外薬局でも使用する事がありますので、処方箋と一緒に受付に出してください。
自己負担上限額管理表は次回の特定医療費受給者証の更新に使用することができるので、ぜひ提出することをおすすめします。
まとめ
難病指定医を受信し、難病と診断された方は通院や入院で医療費がかかるので、特定医療費受給者証を早めに申請しましょう。
医療費受給者証申請から交付までの間に指定医療機関にかかった医療費は払い戻し請求ができるので、領収書などは保管しておきましょう!
最後までお読みくださりありがとうございました。